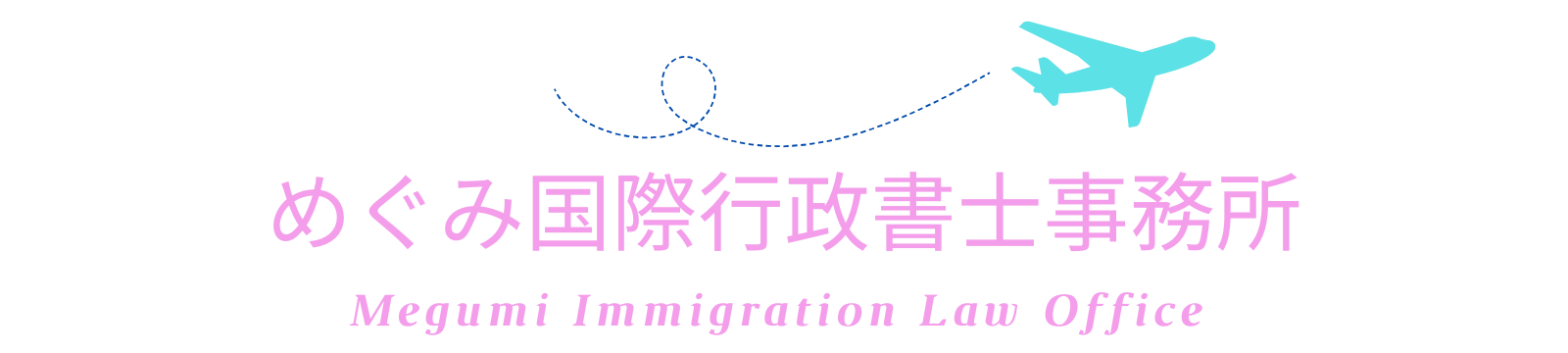【講演会報告】「外国人の方は“一枚岩”ではない」― さんぽ会で伝えた、日本で働く外国人の“本当の悩み”と支援の心

日本で働きながら、
「この手続きで合っているか不安…」
「将来のキャリアやビザ(在留資格)はどうなるんだろう…」
「職場の文化になかなか馴染めない…」
といったお悩みを抱えていらっしゃいませんか?
あるいは、外国人の従業員を雇用されている企業の方で、
「どうサポートすれば、彼ら・彼女らが安心して働ける環境になるのだろう?」
と試行錯誤されているかもしれません。
先日、「さんぽ会(産業保健に関わる方々の会)」の月例会に登壇させていただきました。
「JAPANで働く外国人の安全安心を支えるプロに聞く!」というテーマで、日本で働く外国人の方々が直面するリアルな課題や支援者が大切にしていることについてお話ししてきました。
この記事では、その講演会でお伝えした内容の一部をご紹介します。

産業保健の専門家の皆様へ「外国人労働者のリアル」をお伝えしました
今回、私、鈴木が登壇させていただいたのは「さんぽ会」の第312回月例会です。
産業保健に関わる多くの専門家や学生の皆様が集まる、歴史ある会です。
- テーマ: 「JAPANで働く外国人の安全安心を支えるプロに聞く!外国人労働者のニーズや課題」
- 日時: 2025年11月14日(金)
- 方式: 会場(東京ミッドタウン八重洲)とオンラインのハイブリッド開催
今や、日本で働く外国人の方は増加しており、多くの職場で国籍や文化の異なる仲間と働くことが当たり前になっています。
だからこそ、
「外国人労働者を受け入れる職場の実態は?」
「支援の現場で見えるリアルな課題は?」
「お互いの文化をどう理解し合えばいいの?」
といったテーマを中心にお話ししました。
現役の国際線客室乗務員として多国籍のクルーと共に働いてきた経験、そして行政書士として日々外国人の方々と向き合う中で見えてきた“心の課題”。
その両面から、現場で本当に起きていることや、支援において大切にしたい視点をお伝えしました。

産業保健という、働く方々の『安全安心』を支える最前線にいらっしゃる皆様に、私たち行政書士や支援の現場の生の声をお届けできる、とても貴重な機会でした。
私がお伝えした「最も大切にしていること」
講演会では、私が日頃の業務で感じていること、そして外国人の方々の人生に触れる中で最も大切にしている信念について、4つのポイントでお話ししました。
① 外国人の方は「一枚岩」ではありません
一言で“外国人労働者”といっても、その背景は本当に人それぞれ、千差万別です。
出身国や話す言語が違うのはもちろん、日本に来た理由も、背負っているものも全く異なります。
- 家族を母国に残し、日本での収入で生活を支えている方
- 大きな期待を背負って来日し、仕送りやローン返済など”経済的なプレッシャー”を抱えながら働く方
- ご自身のキャリアアップや学びのために、日本というフィールドを選んだ方
- パートナーとの新しい人生を日本でスタートさせた方
同じ国籍であっても、持っている在留資格(ビザ)によって、日本でできることや将来の見通しはまったく違います。(例:「留学」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」など)



来日直後は“言葉の壁”に悩みますが、長く住むほど“将来への不安”や“家族の問題”が重くのしかかってきます。
滞在年数によっても悩みは変化し続けます。
だからこそ、当事務所では「このお客様にとって、日本で働き、暮らす意味は何か」を理解することを、すべてのサポートの出発点にしています。
お一人おひとりの状況に真摯に向き合い、あなただけの最適なプランを共に考えていきます。
② コミュニケーションの壁が招く「深刻なリスク」
日本での生活、特に初期段階での一番のストレスは、やはり“言葉の壁”です。私自身、学生時代から現在まで、“外国人”として多くの時間を海外で過ごしていますが、母国語ではない環境では、「そうだよね」「わかるよ」という、あいづち一つ打つのにもとても勇気がいります。そしてその一言が言えないだけで周りの人たちとの距離が生まれ、孤独を感じてしまうものです。
孤独が深まると、人との関わりを避け、インターネットやSNSの情報に頼りがちになります。
そこには、残念ながら誤った情報も多く紛れています。



『友人に聞いた』『SNSで見た』という情報を信じて手続きを進めた結果、在留資格を失う(不法滞在)寸前になり、慌ててご相談に来られるケースもあります…。
在留資格を失うことは、日本での生活基盤すべてを失うことを意味します。
だからこそ、正しい情報を、正しいタイミングで企業や専門家が届けることは、皆様の命綱を守ることに直結すると考えています。
また、「日本語を学びたいが、時間もお金もない」という切実な声も多く伺います。
職場が「メンター制度」などを導入し、学びを支える環境を作ることは、日本語能力の向上だけでなく、職場のコミュニティへの参加を促し、孤立を防ぐためにも非常に重要です。
③ 「仕事の常識」は国や文化によって違います
言語の壁と並んで存在するのが、“文化の壁”です。
これは、特に「日常の仕事観」に強く現れます。
例えば、日本では、同僚が忙しそうにしていたら、自分の担当外でも自然に手伝う「助け合い」の光景がよく見られます。
しかし、文化によっては、それが「踏み込みすぎ」と感じられてしまうことがあります。
逆に、自分の担当業務が終われば、周りが忙しくても一息つくのがその人の文化(常識)である場合もあります。



これは、どちらが良い・悪いという話では全くありません。
ただ、お互いが持っている“仕事の捉え方の前提が違うだけ”なんです。
だからこそ、お互いの仕事の常識を事前にすり合わせる作業がとても重要になります。
また宗教は、その方の生活リズムや食事、心の支えと深く結びついています。
礼拝の時間や食事(ハラルなど)への配慮など、「生活の一部としての理解」が、お互いがストレスなく働く環境づくりには欠かせません。
④ 私が「一歩踏み込む」ことを大切にする理由
人は「自分とは違う」と感じた瞬間、無意識に一歩引いて、距離をとってしまいがちです。
しかし、その距離感は、相手に敏感に伝わってしまいます。だからこそ私は、一歩引くのではなく、「一歩踏み込む」ことを大切にしています。
「おはようございます」のあとに、
「よく眠れましたか?」と声をかける。
「おつかれさま」のあとに、
「今日のランチはどうでしたか?」と聞いてみる。
その“ほんの一言”の積み重ねが、異国の地で頑張る外国人の方にとっての「安心感」につながると、私は信じています。



そして、当たり前のことですが、踏み込んだ先にいるのは、日本人と何も変わらない、ひとりの『人』です。
陽気な人もいれば、寡黙な人もいる。仕事が早い人もいれば、ゆっくりな人もいます。
まとめ
今回の「さんぽ会」での講演は、日本で働く外国人の方々が抱える課題の多様性、そして「人」として向き合うことの重要性を改めてお伝えする機会となりました。
めぐみ国際行政書士事務所は、単なる手続きの代行者ではありません。
英語・中国語にも対応し、皆様の文化的背景や、お一人おひとりが抱える複雑な事情を深く理解した上で、あなたの新しい一歩を全力でお手伝いするパートナーです。
「こんなことを相談してもいいのだろうか?」
「自分の状況は複雑すぎて、誰にも分かってもらえないかもしれない…」
そんな不安をお持ちの方も、どうぞご安心ください。
当事務所は、あなたの不安に「心を込めて」寄り添います。
さらに、企業・団体様向けの 在留資格に関する出張相談会や社内向け勉強会、外国人社員サポート体制構築のアドバイス も承っております。
現場のリアルを知る行政書士として、貴社の外国籍社員が安心して働ける環境づくりをお手伝いいたします。
まずは、あなたのお話をお聞かせいただけませんか?
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。
共に、一つひとつの問題をクリアにしていきましょう。


プロフィール
行政書士・鈴木恵。日本と上海の大学を卒業後、約12年間、国際線客室乗務員として勤務。多国籍のお客様との出会いを通じて、日本での留学や就労を目指す方々の夢に触れる。行政書士として、在留資格の申請をはじめとする外国人支援に注力中。
「飛行機を降りたその先にも寄り添える存在に」をモットーに、ひとりひとりの過去・現在・未来を大切に、丁寧にサポートしています。



「こんなことで相談していいのかな?」と思うような小さなことでも、どうぞ気軽にお問い合わせくださいね。